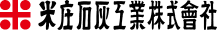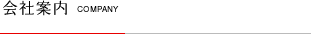津久見地区の石灰岩は津久見市、臼杵市、大野郡野津町にわたり、津久見市の海岸地区の 水晶山 から南西に、国道10号線の泊 、さらに白岩まで、延長20㎞の間に位置する。石灰岩の推定埋蔵量は45億tともいわれている。
津久見の石灰史は、十八世紀後半ごろ、臼杵藩で殖産興業策の一つとして石灰窯業を重視したことから初まります。当初は津久見に石灰役人を置いて事業認可し、窯場の設置、原石の切り出し、売買、運上金に至るまで細かい規定を定めていました。
しかし天保の改革以降、民間業者を下請けにし、上納金を納めさせるように方針転換をしました。そのため文久元年以降になると、津久見で石灰窯業を始める人が増え、慶応三年(1867年)になると、総窯数四十九カ所にのぼるほどに急成長を遂げました。
米庄石灰工業もちょうどそのころ、文久元年(1861年)に徳浦で創業しました。

化学成分表
| 生石灰 | 消石灰 | ||||
| JIS | JIS | ||||
| CaO | % | 95.9 | 93.0以上 | 73.8 | 72.5以上 |
| Ca(OH)2 | % | - | - | 97.5 | - |
| MgO | % | 0.9 | 3.2以下 | 0.6 | 1.0以下 |
| SiO2・AI2O3・Fe2O3 | % | 0.6 | 3.2以下 | 1.0 | 2.0以下 |
| CO2 | % | 1.6 | 2.0以下 | 0.8 | 1.5以下 |
| 150μm残分 | % | - | - | 2.0 | 5.0以下 |